「アライグマの駆除には法律の制限も!有資格者で狩猟免許保有者がわかりやすく解説します!
■記事の信頼性
☆公益社団法人日本ペストコントロール協会会員
☆一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会、感染症予防衛生隊
☆日本ペストロジー学会会員
☆建築物ねずみ昆虫等防除業登録の有る
”すぐくる”総合リビングサービス株式会社の
防除作業監督者で代表取締役の”高橋”が筆者です!

(”すぐくる”総合リビングサービス株式会社 高橋)
「最近、アライグマが家の中を出入りしているのを見かけた……。自分でなんとかしたいけど、野生動物って勝手に駆除しても大丈夫なの?」
そんな不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、アライグマを許可なく駆除するのは、法律に違反する可能性があります。
適切に対処するには、自治体から事前に許可を取るか、追い出し対策などの方法を選ぶ必要があります。
そこで今回は、アライグマ駆除に関係する法律や、合法的に捕獲する方法、許可なしでできる対策などを、害獣駆除のプロの視点からわかりやすくご紹介します。
目次
アライグマの駆除が法律違反になる可能性も
アライグマ対策に関係する主な法律
・「鳥獣保護管理法」について
・「特定外来生物法」のポイント
法律に則ってアライグマを捕まえるには?
・行政から捕獲許可を取る方法
・狩猟免許の取得について
手続き不要でできるアライグマ対策
・住まいの環境を整えて予防する
・嫌がるものを使って追い出す
・侵入口をふさいで再侵入を防ぐ
アライグマ対策は公益社団法人日本ペストコントロール協会会員の”すぐくる”にお任せください!
まとめ|安心・安全なアライグマ対処法とは
アライグマの駆除が法律違反になる可能性も

アライグマは見た目が愛らしい動物ですが、実際には家に住み着いてフンやゴミで汚したり、敷地内の作物やペット、小動物などを荒らすこともある、厄介な害獣として知られています。
とはいえ、アライグマは「鳥獣保護管理法」や「特定外来生物法」などの法律によって保護・規制されており、毒餌を使ったり、無許可で捕まえたりする行為は法律違反になります。
つまり、たとえ自宅で被害が発生していても、自己判断で駆除や捕獲を行ってしまうと、法律に違反したとして罰せられる可能性があるのです。
アライグマ対策に関係する主な法律

ここでは、アライグマを駆除する際に必ず押さえておきたい2つの法律について解説します。
それぞれの法律がアライグマ駆除に対してどのようなルールを設けているのかをわかりやすく取り上げますので、違反を避けるためにも、しっかりと内容を確認しておきましょう。
「鳥獣保護管理法」について
鳥獣保護管理法(正式名称:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)は、野生動物が乱獲されるのを防ぐために制定された法律です。
この法律では、アライグマを毒餌で駆除したり、捕まえたりするなど、傷つける可能性のある行為を行う場合には、事前に行政機関(市役所・保健所・地方環境事務所など)から許可を得る必要があると定められています(第83条)。
この法律に違反して、無断でアライグマを駆除・捕獲した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるため、十分に注意が必要です。
また、捕獲後に許可を得ずにアライグマをペットとして飼うことも法律で禁止されています。これに違反すると、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(第84条)。
ペットとしての飼育だけでなく、譲渡・譲り受け・販売なども禁じられているため、こうした行為は絶対に避けましょう。
「特定外来生物法」のポイント
特定外来生物法(正式名称:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)は、生態系や人間の生活、農林水産業への被害を防ぐことを目的に定められた法律です。
この法律では、特定外来生物に指定されているアライグマを対象に、捕獲や運搬を伴う防除(=予防や駆除)を行う場合には、「防除の公示」や「防除の確認・認定」といった手続きを事前に行う必要があるとされています。ここでいう「防除」とは、簡単に言えば害獣を駆除したり、その被害を未然に防いだりすることを指します。
さらに、捕獲したアライグマを許可なく野外に放す行為も法律で禁じられており、これに違反した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があるため、十分に注意しましょう(第9条・第32条)。
法律に則ってアライグマを捕まえるには?
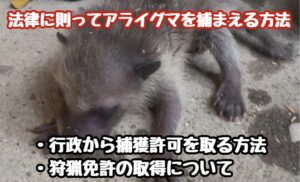
アライグマを自分で法律に則って捕獲するには、「鳥獣保護管理法」と「特定外来生物法」の規定を守る必要があります。
そのうえで適法に対応する方法としては、次の2つの手段があります。
・行政から捕獲許可をもらう
・狩猟免許を取得する
ここからは、それぞれの方法について詳しくご紹介していきます。
行政から捕獲許可を取る方法
捕獲許可の申請は、お住まいの市役所や保健所など、地域の行政機関で行う必要があります。埼玉県内でも市町村によって申請方法や対応が異なり、そもそも個人での捕獲申請を受け付けていない地域もあるため、まずはお住まいの自治体に確認してみましょう。
アライグマの捕獲許可を取得するためには、自治体が指定する書類を揃えて提出する必要があります。参考までに、埼玉県で申請を行う際に求められる主な書類を以下に挙げます。
・アライグマ捕獲許可申請書
・捕獲場所の地図(被害のあった場所や設置予定のわなの位置)
・害獣による被害状況の報告書や写真
・実施者の情報(個人または団体の連絡先や氏名)
・鳥獣捕獲従事者証の写し(必要に応じて)
このように、申請には複数の書類が必要になるため、事前準備が重要です。また、捕獲許可が交付されるまでには、自治体によって1週間から数週間程度かかる場合があるため、早めに対応することをおすすめします。
狩猟免許の取得について(埼玉県の場合)
アライグマの捕獲には、狩猟免許の中でも「わな猟免許」を取得する方法があります。
狩猟免許を取得するためには、埼玉県が実施する狩猟免許試験に合格する必要があります。試験の日程や試験会場は地域によって異なるため、埼玉県内での詳細については、埼玉県環境部または地域の猟友会に問い合わせることをおすすめします。
狩猟免許試験に合格すれば、正式に狩猟免許を取得できますが、アライグマを実際に捕獲するためには、事前に埼玉県で「狩猟者登録」を行い、所定の狩猟税を納める必要があります。
「わな猟免許」を使ってアライグマを捕獲するには、これらの手続きをしっかりと踏まなければならず、時間とお金がかかることを覚悟しておく必要があります。実際にアライグマによる被害が発生してから免許を取得するのでは、迅速に問題解決を図るのは難しいため、早めに準備を進めておくことが重要です。
手続き不要でできるアライグマ対策

アライグマを自分で捕獲する場合は、捕獲許可や狩猟免許といった手続きが必要ですが、これらを行わずに取り組める対策も存在します。
許可などの申請をせずに実施できるアライグマ対策としては、以下のような方法が一般的です。
「住まいの環境を整えて予防する」「嫌がるものを使って追い出す」「侵入口をふさいで再侵入を防ぐ」といった方法を理解しておくことで、ご家庭でも実践可能なアライグマ対策に役立てることができます。
それぞれの対策をしっかり把握し、被害の予防にお役立てください。
住まいの環境を整えて予防する
まずは、自宅やその周辺環境を整え、アライグマに餌となるものを見せない工夫をすることが大切です。餌が見える場所にあると、アライグマは本能的に引き寄せられてしまいます。
アライグマは雑食性のため、家庭菜園の野菜や果物、生ゴミなど、あらゆるものに興味を示します。特に埼玉県内では郊外や住宅地の近くに畑や庭があるご家庭も多く、アライグマが出没しやすい環境がそろっているケースも少なくありません。
そのため、次のような対策を日頃から心がけましょう。
・生ゴミはしっかり密封し、できるだけ早めに処分する
・畑や家庭菜園の周囲には、高めの柵を設置して侵入を防ぐ
・塀や屋根に登られないよう、家の周りの木の枝は剪定しておく
嫌がるものを使って追い出す
アライグマを追い出す方法としては、忌避剤やくん煙剤の使用も有効です。これらの対策グッズは、ホームセンターやオンラインショップなどで簡単に手に入れることができます。
忌避剤やくん煙剤には、アライグマや他の害獣・害虫が嫌がるニオイ成分が含まれており、アライグマ専用の製品を使えば、ニオイによって家の中から追い出すことが可能です。
ただし、これらの製品は密閉された場所で使用しないと十分な効果が得られないうえ、持続性にも限りがあるため、根本的な解決というよりは一時的な応急処置と考えるのが良いでしょう。
侵入口をふさいで再侵入を防ぐ
忌避剤やくん煙剤を使えば、自宅でも比較的簡単にアライグマ対策を始めることができますが、これだけでは再び家に入り込まれる恐れがあります。アライグマによる被害を繰り返さないためには、追い出した後に侵入経路をしっかり塞ぐことが重要です。
アライグマが侵入してくる代表的な場所としては、「屋根裏周辺のわずかな隙間」や「床下の通気口」などが挙げられます。しかし、アライグマは直径10cmほどの狭い隙間があれば侵入できるため、全ての侵入口を見つけて完全に封鎖するのは簡単ではありません。
わずかな侵入口が残っているだけでも再侵入の可能性があるため、不安がある場合は、経験豊富な害獣駆除の専門業者に相談することをおすすめします。
公益社団法人日本ペストコントロール協会会員の”すぐくる”にお任せください!
アライグマによる被害を受けた際は、できるだけ早く対処することが重要です。ただし、駆除や捕獲を行う際には、法律を順守する必要があります。
とはいえ、捕獲に必要な許可申請や狩猟免許の取得には時間と手間がかかるうえ、手続きなしで行える対策も、侵入経路を完全に塞げなければ意味をなしません。
そのため、アライグマを合法的かつ確実に、そしてスムーズに駆除したいと考えるなら、専門の駆除業者(中でも公益社団法人日本ペストコントロール協会会員の事業者)への依頼が最も現実的な選択肢です。信頼できる業者をお探しなら、私たち”すぐくる”総合リビングサービス株式会社にお任せください。
弊社はすべて自社施工で対応しており、初回のお問い合わせから駆除作業、アフターケアまで一貫して自社で対応しています。
外部の下請けを介さないため、予算に応じた最適な対応プランをご提案できるのも特長です。同じ説明を複数の業者に何度も繰り返すようなご負担もありません。
また、”すぐくる”総合リビングサービス株式会社では再発を防ぐための対策も徹底しており、場合によって、ご依頼に対して保証をお付けしています(保証内容や期間は現地調査の際に詳しくご案内いたします)。
アライグマの被害にお悩みでしたら、状況が悪化する前にお気軽にご相談ください。
ネズミやハクビシン・コウモリ等の害獣やトコジラミやシロアリ・ゴキブリ等の害虫でお悩みの方は
☆公益社団法人日本ペストコントロール協会会員
☆一般社団法人埼玉県ペストコントロール協会、感染症予防衛生隊
☆日本ペストロジー学会会員
☆建築物ねずみ昆虫等防除業登録の有る
”すぐくる”総合リビングサービス株式会社へご相談ください。
無料相談ダイヤル
📞0120-979-878


